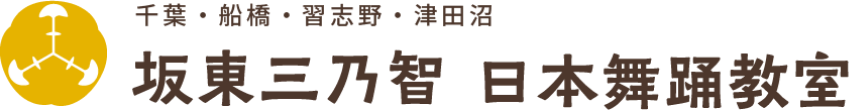お稽古はゆかたでOK
日本舞踊をやってみたいけど、一歩踏み出せない人の結構大きなハードルとなっているのが、「きもの」なのではないでしょうか。
体験レッスンや見学に来られた方が、「ゆかたを持っていますが、日本舞踊に適しているのでしょうか?」「ゆかたを持っていますが、よく着られません」等とおっしゃるのも、きものを着られないことに不安を感じられるからかと思います。
日本舞踊はきものをキッチリ着て踊るもの、というイメージが強いようです。しかし、お稽古はゆかたで行っています。
「ゆかたでいいんです!」と言うと、皆さん「ゆかたでいいんですか?!」とビックリされます。
ときどき歌舞伎役者さんがお稽古されているのをテレビで取り上げているのを見たことがありませんか。それを見ても、役者さんはゆかたを着ています。
ゆかたはきものの中で最もカジュアルな普段着で、お稽古にも適しています。というのは、汗をかいたとき、洗濯しやすいからです(家の洗濯機で洗えます)。

ゆかたはたたんでネットに入れ、洗濯機のおしゃれ着コースで洗う(左)。
袖に物干し竿を通して干すとシワにならずアイロンがけの必要がない
ゆかたは着付けを学ぶ際にも、最もシンプルな入門編を学べます。ですので、ゆかたをお持ちでタンスにしまってあるという方は、胸を張って持ってきて下さい。
今日は、初心者の人がきものを無理なく揃える方法について書きます。
春から夏にかけてなら、ゆかたと半幅帯を買う
近頃は、夏に入る前になると、きもの屋さんだけでなく、スーパーの洋服売り場でもゆかたが並べられることがあります。既製品のゆかたは、だいたいフリーサイズで、安いものは1000円台から買えたりするのは、大量生産ができるからでしょう。お祭りや花火大会にも行けるように、帯と下駄がセットで買えることも多いですね。

ゆかたと半幅帯の一例。このゆかたは既製品でなく反物から仕立てたもの
さて、ゆかた+帯の他にも、着るために必要なものがあります。それは、腰ひもです。
温泉旅館やホテルなどに行くと、ゆかたと細い帯が置いてありますね。温泉のゆかたは、袖に手を通して、前見頃を重ね、ウエストを細帯でくるっと巻いて、結ぶだけ。誰でも着られると思います。でも何となく、前がはだけやすいのが不安ですね。
ゆかたを着るときには、腰ひも2本が必須です。なければ、きもの屋さんやネットでも数百円で買えます。もしもお母様かお祖母様がきものをお持ちなら、腰ひもの2本や3本はお持ちでしょう。タンスに眠っているかもしれません。あれば買う必要はありません。

腰ひも2本は必需品
あとは、ゆかたの下に着る下着(肌着)ですが、通常は、肌襦袢(はだじゅばん)と裾よけ(すそよけ)というものを付けます。
最近のもので、肌襦袢と裾よけが一体のワンピース型のものが売っています。これはササッと着られて便利かもしれませんが、日舞では足を結構使うので、ワンピース型だと前がはだけてしまうため、適しません。できるだけ、肌襦袢と裾よけを買って下さい。

肌襦袢(左)と裾よけの例

肌襦袢と裾よけが一体型になっているものは踊るのには適しません
男の踊りになりますと、足を大きく広げたり、高く上げたり、ジャンプすることもありますので、ステテコをはくと足が動かしやすくてよいですよ。きもの屋さんでは、「踊り用」のステテコを売っています。
お稽古に足袋は必須です。ない場合、初めての方は、しっかりした靴下(できれば白)を持ってきて下さい。すり足、拍子(足を踏みならす動作)、おすべり(足の裏を床にすべらせる動作)などを行うため、素足やストッキングは適さないのです。

足袋の例(左)。底がしっかりしている方が踊りやすい。足袋の代用の靴下はしっかりしたもの。
白が推奨されるのはお稽古場を汚さないという意味がある
以上、一番はじめに揃えるものをまとめますと、
- ①ゆかた
- ②半幅帯
- ③腰ひも2本
- ④肌着(肌襦袢と裾よけ)
- ⑤足袋
ということになります。
最低限これだけあれば、日本舞踊のお稽古はできます。
体験レッスンでは、お貸しすることも可能ですので、おっしゃってください(レンタル料500円をいただきますね)。
また、当教室では、きものを着る体型補正のために、さらしとタオルを使っています(体験レッスンの時に説明します)。上記の他に、⑥普通のフェースタオル1枚、着付けお助けグッズとして、⑦洗濯ばさみを1個お持ち下さい。
手軽に買えてお手入れの簡単なきものから始める
さて、冬になると、ゆかたでは少し寒くなります。袷(あわせ)のきものの方があたたかくてよいでしょう。袷というのは、裏地がついていて、秋~冬~春に着るきものです。
日本舞踊を始めたい人は、きものも着られるようになりたい、という夢もお持ちだと思います。しかし、どこから始めたらいいか?と迷われるでしょう。踊りのお稽古では汗をかくこともありますから、手軽に買えてお手入れの簡単なポリエステルのきものから、少しずつ揃えていったらよいと思います(きものの知識も徐々についていきます!)。
ゆかたの次に手軽に買えるのは、既製品です。いわゆる「プレタきもの」と呼ばれているもので、すでに仕立て上がっていて、SMLなどのサイズになっています。お値段も数千円~と、洋服を買う感覚で買えます。

ポリエステルのプレタきものの例。2着で7000円と安かった
ゆかたと違うのは、肌着ときものの間にもう一枚、長襦袢というものを着ることです。きものの下に着て、襟、または袖をチラリと見せるものです。長襦袢にも既製品があり、二部式(上半身、下半身に分かれているもの)と一部式があります(既製品なら値段は数千円程度)。

長襦袢の一部式(左)と二部式の例。写真では、一部式はあつらえたもの、二部式は既製品です
日本舞踊では、男踊りのとき股を割ることが多いので、長襦袢は二部式がよいといわれています。
買うのはネットか、お近くのきもの屋さんが便利だと思います。ネットは数が豊富ですが、豊富すぎて知識がないときはなかなか難しく感じるかもしれません。きもの屋さんは、最初入るときは敷居が高いかもしれませんが、「初心者で、手始めにポリエステルの既製品を買いたい」と目的意識をハッキリ伝えれば、店員さんがいろいろと教えてくれます。
最近のきもの屋さんは、買った人向けに、無料あるいは安く着付けレッスンをしてくれるところもありますから、それを利用するのもよいと思います。
帯は、最初のうちは、ゆかたと同じ半幅帯でよいのです。肌着の上に、長襦袢を着て、きものを着て、その上に半幅帯を締めます。本格的な太い帯でお太鼓に締めるのは少し難しいので、次のステップでよいと思います。
ゆかたの次に買ったらよいものをまとめますと、
- ⑥ポリエステルのプレタきもの
- ⑦長襦袢(一部式もしくは二部式。日本舞踊では二部式がベター)
となります。
また、帯を締めるときに便利なグッズとして、
- ⑧帯板(帯がデコボコにならない)
- ⑨伊達締め(きものの胸まわりを整理できる)
- ⑩帯締め(半幅帯でも「矢の字」という結び方では、結び目を押さえるために使う。帯締めは帯との組み合わせでおしゃれができる)
があります。必須ではありませんが、徐々に揃えていくとよいでしょう。

帯板の例(左)、伊達締めの例(真ん中)、帯締めの例(右)
中古をネットショップで買う。着なくなった人からいただく
きもの人口の減少により、私達の前の世代が手放したきものや帯がまわりまわって中古のネットショップで売られるようになりました。
リサイクルショップの良いところは、絹織物を手頃な値段で買えることです。フォーマルの袋帯など普通気軽に買える値段ではありませんが、リサイクルショップなら手が出ます。
そして、昔の絹織物は今の絹より間違いなく良いものが多いといわれています。蚕の育て方からして昔は丁寧に育てていたからだそうです。
ただ、昔のきものは昔の人の体型に合わせてなので短い!とくに裄(ゆきとはほぼ腕の長さ)が短い場合が多いですね。日本舞踊は、袖を使う動作が多いので、裄は長めがよいのです。ネットで買う場合、寸法が書いてありますから、少なくとも自分の身丈、裄丈を把握しておくとよいでしょう。
また、きものを着るようになると、きものが向こうからやってくることがあります。つまり、着なくなった人から譲られることも多くなるのです。
母や祖母からきものをもらい、自分サイズに仕立て直して着ているものもあります。
教室では、若い人が、先輩から「若いときに着ていたけど、歳をとって着られなくなっちゃったからあげるわ」ということがしばしば起こります。これは、きものを着られるからこその特権です。
きものを知れば知るほど、その価値がわかり、捨てることができません。いただいたり、自分がゆずったりして人の手をわたっていきます。いただいたきものや帯をどうコーディネートするのかを考えるのも楽しいものです。そういう楽しさを、一人でも多くの人に味わっていただければと思うのです。
このコラムにあるようにだんだんと、きものときものまわりの小物、自分にとっての便利グッズなどを揃えていき、着付けやきものの知識も身につけていくと、楽しみが広がるのではないかと思います。
最後までお読みいただきありがとうございます。
日本舞踊やってみたい!と思われた方は、ぜひ無料体験レッスンにお越しください。